トップページ > 慢性上咽頭炎
慢性上咽頭炎
Q:慢性上咽頭炎とはどんな病気ですか?
![]()
上咽頭の位置 – 口蓋垂(いわゆるのどちんこ)のさらに上部、鼻の突き当たりにある部分が上咽頭(じょういんとう)です。この上咽頭が慢性的に炎症を起こしている状態を慢性上咽頭炎といいます。のど(咽頭)は上咽頭・中咽頭・下咽頭の3つに分かれますが、上咽頭は鼻から吸い込んだホコリや細菌・ウイルスなどが真っ先に付着しやすい「空気の通り道」です。そのため上咽頭には身体を守るリンパ球(免疫細胞)が多く存在し、健康な人でも常に軽い炎症(生理的炎症)が起きているほど活発な免疫器官です。
ところが風邪や体調不良でさらに炎症が強くなり、その炎症がおさまらず何度も繰り返す状態になると慢性上咽頭炎になります。
慢性上咽頭炎は、実はとても身近なのに見逃されやすい病気です。たとえば、「朝起きると喉に痰がからんでいる」「喉の奥がイガイガ、ヒリヒリする」「ずっと喉の奥に何か詰まっている感じがする」こうした症状で耳鼻科や内科を受診しても、「異常ありません」と言われてしまうケースです。
これは、内視鏡で見える範囲が中咽頭や下咽頭に限られており、炎症の本当の原因である“上咽頭”まではしっかり観察されないことが多いからです。炎症止めや去痰薬を処方されてもなかなか良くならず、原因が分からないまま「仕方ない」と諦めてしまう方も少なくありません。
実際には、これらの不快な症状の根本に“鼻の奥=上咽頭”の炎症が潜んでいることがとても多いのです。ところが、医学の教科書にもほとんど載っていないため、医師のあいだでも十分に認識されていないのが現状です。
Q:慢性上咽頭炎とはどんな症状ですか?
![]()
慢性上咽頭炎の症状は、喉や鼻の不調に留まらず全身の不調へと多岐にわたることが特徴です。 上咽頭は鼻や喉の症状だけでなく耳や神経、免疫系にも影響を及ぼすため、「もしかして自分も?」と思われるような一見バラバラな不調が実は慢性上咽頭炎に関連している場合があります。
主な症状はその原因となるメカニズムを大きく3つのグループに分類できます
■1 上咽頭の炎症そのもの、または炎症の広がりによる直接的な症状
上咽頭周辺の局所症状や、炎症による関連痛が生じます。
- 喉の痛み・ヒリヒリ感、鼻とのどの間の違和感・乾燥感
- 後鼻漏(鼻の奥から喉に鼻水が垂れる)、常に痰が絡む感じ
- 咳払い、慢性的な咳
- 声がかすれる、鼻の奥に嫌なニオイを感じる
- 首こり、肩こり、頭痛、頭重感(頭が重い感じ)
- めまい(ふわふわと浮くようなタイプ)や耳閉感(耳が詰まった感じ)
- 顎や耳の下の痛み、舌のヒリヒリ感、歯の痛み(知覚過敏)、顎関節の痛み
- 微熱が続く、痰に血が混じる など
上咽頭は多くの神経が集まる、とても敏感な場所です。そのため炎症が起きると喉だけでなく近接する首・肩・頭部などにも関連痛が広がりやすいと言われます。
実際、「ひどい関節の痛み、肩こりだと思ったらインフルエンザの始まりだった」という経験はありませんか?それはインフルエンザで急性上咽頭炎が起き、炎症が首や肩の神経を刺激して肩こり・頭痛を引き起こした例です。慢性上咽頭炎でも同様に、首や肩のこり・痛み、頭痛がしばしば現れます。
■2 自律神経の乱れによる症状
上咽頭の炎症が脳の自律神経中枢に影響を及ぼし、全身的な不調を招く場合があります。
- 全身の倦怠感(だるさ)、慢性疲労
- めまい、立ちくらみ、起立性調節障害(朝起きられない)
- 睡眠障害(不眠・過度な眠気)
- 集中力や記憶力の低下、イライラ感
- 胃腸の不調(胃もたれ、胃痛、吐き気)、過敏性腸症候群(下痢や便秘を繰り返す)
- うつ症状(意欲の低下、抑うつ気分)
上咽頭は自律神経をつかさどる延髄・視床下部に近い位置にあります。また迷走神経という全身の臓器に影響する神経が通っているため、上咽頭炎があるとこの神経が刺激されて全身倦怠感、めまい、胃腸の不調など様々な原因不明の不調が起こる可能性があります。
検査をしても異常が見つからないため「気のせい」「自律神経失調症」や気持の問題と言われ軽い鬱と診断されてしまうこともあります。原因不明の体調不良が続くとき、慢性上咽頭炎が隠れていないか疑ってみることも必要です。
■3 免疫反応による二次疾患(病巣感染症)
上咽頭の慢性炎症が発端となり、免疫システムの異常から遠く離れた臓器に炎症を引き起こす病気が生じることがあります。
- 腎臓の炎症(IgA腎症、ネフローゼ症候群)
- 関節の炎症(関節炎、胸肋鎖骨過形成症 など)
- 皮膚の炎症(掌蹠膿疱症、乾癬、慢性湿疹、アトピー性皮膚炎 など)
本来、免疫細胞は身体を守る存在ですが、慢性上咽頭炎ではリンパ球や単球などが過剰に活性化され、炎症物質(サイトカイン)も大量に出ます。これらが血液に乗って全身を巡るうちに、腎臓や関節、皮膚といった離れた場所で炎症を誘発することがあります。このように上咽頭の炎症が「病巣」となって起こる二次的な病気を病巣感染症と呼びます。
例えば風邪(上咽頭炎)をきっかけに腎臓病や皮膚病が悪化・発症するケースは昔から知られており、「風邪は万病のもと」という言葉もあるほどです。慢性上咽頭炎があると、こうした自己免疫的な反応で全身に炎症を起こしやすくなる可能性があります。
以上のように、慢性上咽頭炎が関与しうる症状は喉や鼻の局所症状から全身の不調まで実に多彩です。
「長年原因不明の症状に悩んでいるけれど検査では異常なし」と言われた方は、慢性上咽頭炎が隠れた原因になっていないか、一度専門医に相談してみるとよいでしょう。
Q:慢性上咽頭炎の原因は何ですか?
![]()
慢性上咽頭炎の原因は明確に解明されていませんが、発症や悪化の要因として次のようなものが考えられています。
- 細菌やウイルス感染(風邪をきっかけに発症することが多い)
- 体の冷え(特に首まわりの冷え)
- 疲労や睡眠不足、ストレスによる自律神経の乱れ
- 空気の乾燥や口呼吸(就寝中にのどが乾燥すると炎症が起きやすい)
- 鼻炎・副鼻腔炎による鼻づまりや後鼻漏(鼻水が喉に流れる刺激)
- 逆流性食道炎(胃酸が上咽頭まで上がる刺激)
- タバコの煙や粉塵、黄砂など刺激物質の吸入
- 天候や気圧の変化、寒冷環境
このように、感染症だけでなく寒さや乾燥、自律神経の乱れ、胃酸の逆流など様々な要因で上咽頭は炎症を起こします。
特に「首の冷え」がある人は、慢性上咽頭炎に伴って肩こりや首こりが強くなることがあります。首まわりを温めたり、血行を改善する漢方薬(葛根湯など)で症状が和らぐこともあります。
就寝中の口呼吸で喉が乾燥する人は寝室の加湿や鼻づまりの治療(点鼻薬や抗アレルギー薬)によって症状改善が期待できます。
Q:慢性上咽頭炎はどのように診断されますか?
![]()
慢性上咽頭炎の診断は、まず医師が症状について詳しくお話を聞き、そのうえで小さなカメラ(内視鏡)で鼻の奥にある上咽頭をのぞきます。炎症があると、粘膜が赤く腫れていたり、粘液や後鼻漏という膿の有無を観察します。また、上咽頭の粘膜擦過療法(Endoscopic Epipharyngeal Abrasive Therapy :E-EAT)という方法で上咽頭をこする処置で、出血が生じるかどうかなどの項目をチェックして診断します。
セルフチェック方法として、首すじ(胸鎖乳突筋や僧帽筋と呼ばれる部分)を指で押して強く痛む場合は、上咽頭の炎症が首や肩の筋肉に影響している可能性があります。ただし、これはあくまで個人の目安であり、はっきりした診断にはなりません。
Q:慢性上咽頭炎のセルフケアはありますか?
![]()
慢性上咽頭炎の原因は多岐にわたりますが、日常生活で気をつけたり、実践したりすることで、症状の改善や悪化の予防ができる方法がいくつかあります。
■1. 体の冷え対策:
特に首まわりを冷やさないように心がけましょう。
ヨガやシャワーなどで身体や首元を温めることは、血流を改善し、症状の緩和に繋がる可能性があります。
■2. 疲労・睡眠不足・ストレスの管理:
十分な睡眠をとり、心身の疲労をためないことが重要です。
ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、炎症を悪化させる要因となります。リラックスできる時間を作り、ストレスを適切に管理しましょう。
■3. 空気の乾燥対策:
乾燥した空気は上咽頭の炎症を悪化させます。加湿器を使用するなどして、室内の湿度を適切に保ちましょう。
特に夜間の口呼吸はのどの乾燥を招きやすいので、意識して鼻呼吸を心がけたり、必要に応じて口呼吸防止テープなども活用したりすると良いでしょう。
■4. 正しい鼻うがい:
鼻の中の余分な粘液や膿を洗い流し、症状の悪化を予防することができます。
方法:
体温程度のぬるま湯200mlに対し、食塩小さじ1/2程度(約0.9%の生理食塩水)を混ぜて用意します。市販の鼻うがい用生理食塩水も活用できます。
専用の鼻うがい容器を使い、片方の鼻の穴からゆっくりと液を流し込み、反対側の鼻の穴や口から自然に流れ出るようにします。口を軽く開けて行うと楽にできます。
水道水やお風呂の水、海水など、人間の塩分濃度と異なる液体をそのまま鼻に入れると粘膜を傷める可能性があるので避けましょう。
Q:慢性上咽頭炎で避けたほうがよいことはなんですか?
![]()
- 喫煙:
タバコは鼻や喉の粘膜を強く刺激し、炎症を長引かせます。 - 過度の飲酒:
アルコールで血管が広がると、鼻粘膜の腫れや詰まりが悪化します。 - 市販点鼻薬の使いすぎ:
長期間の使用でかえって鼻づまりを悪化させることがあります。 - アレルギーの原因物質:
花粉やハウスダスト、ペットの毛など、できるだけ接触を減らしましょう。
これらはあくまで症状を和らげるための生活上の工夫です。症状が続く、悪化する場合には自己判断せず、専門医にご相談ください。
Q:慢性上咽頭炎の治療法にはどのようなものがありますか?
![]()
医療機関では、症状の原因となっている炎症を抑えるための様々な治療が行われます。
■内服薬
炎症を抑える消炎剤、粘り気の強い鼻水をサラサラにする粘液調整剤(去痰薬)、細菌感染が疑われる場合の抗生物質などが処方されることがあります。
■Bスポット療法(内視鏡下上咽頭擦過治療:E-EAT)
細長い綿棒に薬(塩化亜鉛の液)をしみこませ、鼻の奥の炎症部分を直接こすって炎症を落ち着かせます。診断と治療を同時に行えるのが大きな特徴です。
以前は盲目的(何も観察しないで鼻の穴から綿棒を医師が突っ込んで、上咽頭をこすっていた)に行っていたが、2010年ころから内視鏡で実際に上咽頭の粘膜を観察しながら行なう方法(E-EAT)が開発され、現在ではこの手法が主流となっています。
治療は 週に1〜2回のペースで、10回あるいはそれ以上受けるものです。症状が軽症の場合は1か月ほどで良くなることもありますが、症状が重い方は数か月以上かかることもあります。治療の際には、炎症が強いほど「ツーン」とした強烈な痛みやしみる感覚があり、涙が出たり、頭の奥に響くような不快感も伴います。また、しばらくの間は鼻水に血が混じることもあります。効果には個人差が大きく、治療の継続が必要となる場合や、効果を実感できないケースもあります。
■ネブライザー治療(吸入治療)
薬液を霧状にして鼻やのどに吸入することで、炎症部位に直接薬剤を届け、症状の緩和を図ります。これらの治療法は、慢性上咽頭炎の症状改善に有効とされていますが、患者様の状態や症状の種類によって、最適な治療法は異なります。
■カテーテル治療
下記に詳しく説明しますが、炎症を抑えるための新しい方法です。炎症でできた異常な血管を減らすことで、炎症が改善されます。日帰りで20-30分ほどででき、痛みもほとんどありません。詳しくは次の項目を参考にしてください。
Q:慢性的な上咽頭炎で悩んでいます。のどの違和感や痰が続き、集中力も落ちてしまって日常生活に支障があります。EATをうけたり鼻うがいや薬など自分なりに工夫はしてきましたが、なかなか根本的に良くなりません。何か新しい治療はありませんか?
![]()
慢性上咽頭炎に限らずすべての慢性炎症において、治りにくい炎症の背景に、「モヤモヤ血管」と呼ばれる異常な血管の増殖が関わっていることが分かってきています。
この慢性炎症に対する新しい治療法として注目されているのが、カテーテル治療(血管内治療)です。もともとは五十肩や膝関節の慢性炎症の治療として普及してきましたが、近年は声帯炎や慢性上咽頭炎などの長引く炎症にも応用できることが明らかになっています。
カテーテル治療では、点滴で使用するような極細チューブ(直径約0.6mm)を鼠蹊部から挿入し、炎症が起きている上咽頭の血管までアプローチします。そこで炎症の原因であるモヤモヤ血管に薬剤を流し、治療することで炎症と痛みの悪循環を断ち切ります。この治療は約30分で完了し、入院は不要な日帰り治療です。治療後はカテーテルを抜き取るため体内に何も残らず、傷跡はバンドエイドで処置する身体に負担がかからない方法です。
治療実例
体の不調の陰に隠れた「のどの奥の炎症」慢性上咽頭炎のカテーテル治療
慢性上咽頭炎は「根本的な治療がない」と思われがちですが、モヤモヤ血管にアプローチするカテーテル治療という新しい選択肢があります。なかなか改善しない症状でお悩みの方は、ぜひ専門の医療機関を受診し、ご自身の状態に合った治療法について相談されることをおすすめします。
<参考文献・出典>
日本病巣疾患研究会 「慢性上咽頭炎」 https://jfir.jp/chronic-epipharyngitis/
原渕 保明. 慢性上咽頭炎に対する上咽頭擦過療法, 日耳鼻 128: 205-214, 2025
奥野祐次 モヤモヤ血管に関する研究「異常血管(モヤモヤ血管)が慢性痛に関与する仕組み」
オクノクリニック公開資料及び関連学会報告よりカテーテル治療による炎症血管塞栓の症例報告
著者プロフィール
奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)
オクノクリニック 総院長
専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)
2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。
現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約
![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)
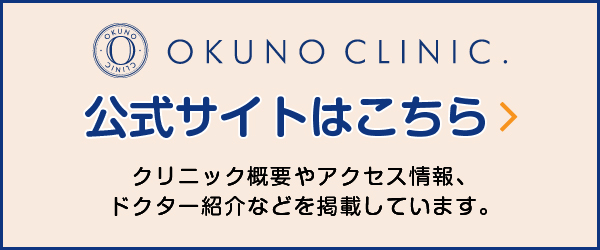
![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)