トップページ > 円形脱毛症(脱毛症)
円形脱毛症
Q:円形脱毛症(脱毛症)とは何ですか?
![]()
脱毛症は、ある日突然に頭髪や体毛の一部が丸く抜け落ちてしまう疾患です。本来はウイルスや細菌などの外敵から身体を守るための免疫機能が、間違えて自分の髪の毛の組織(毛包)を攻撃してしまうことで生じる自己免疫疾患の一種です。
小さな10円玉大の脱毛斑が1個だけ現れる場合もあれば、複数箇所に生じたり、重症では頭全体や全身の毛が抜けてしまったりすることもあります。見た目の変化により「また抜けてしまうのでは…」という不安やストレスを感じやすく、周囲の目も気になるため、患者さんにとって精神的負担の大きい病気です。
頭皮の脱毛症には円形脱毛症、男性型脱毛症、女性型脱毛症、薬剤性脱毛、抜毛症(トリコチロマニア)などがありますが、ここでは円形脱毛症(以降脱毛症)について紹介します。
Q:円形脱毛症はどんな症状がありますか?
![]()
円形脱毛症(えんけいだつもうしょう)の主症状は文字通り脱毛です。髪が抜けてしまう部位のことを脱毛斑と呼びます。脱毛斑の箇所では、髪の毛を引っ張ると抜けていってしまうようになります。脱毛以外の症状は無いか軽度であることが多いです。軽度のかゆみや刺激感、発赤を伴うことがあります。自覚症状がほとんど出にくいため、「いつの間にか円形のハゲができていた」という形で気づくことも少なくありません。
脱毛斑は頭皮に1ヶ所だけできることもあれば、複数できること(多発型)、広がって頭髪のほとんどが抜けること(全頭型)、さらには眉毛・まつ毛・体毛まで全て抜けること(汎発型)もあります。脱毛斑の周囲には、先が細く根元が太い「感嘆符毛」と呼ばれる短い毛や、黒い点状の毛根が見られることがあります。このように症状の現れ方や重症度には個人差があり、1回きりで自然に治る軽症の方もいれば、再発を繰り返し長期の治療が必要な方もいらっしゃいます。
■円形脱毛症のタイプ(分類)
- 単発型:
1か所だけに小さな脱毛斑ができる - 多発型:
複数の脱毛斑が同時に生じる - 全頭型脱毛症:
頭髪の大部分、またはすべてが抜けてしまうタイプ。短期間で急速に進行することもあり、治療抵抗性を示すことが多く、回復までに時間がかかる場合があります。 - 汎発型脱毛症(全身脱毛症):
頭髪に加え、眉毛・まつ毛・ひげ・体毛まで全身の毛が抜けるタイプ。最も重症とされ、長期的な治療や再発予防が必要になることがあります。
Q:円形脱毛症の原因は何ですか?
![]()
脱毛症の最大の原因は「自己免疫反応」です。私たちの免疫システムは通常、細菌やウイルスなどの外敵から身を守っていますが、何らかのきっかけでこの免疫が誤作動を起こし、本来守るべき自分自身の組織を攻撃してしまうことがあります。このような現象を「自己免疫疾患」と呼び、円形脱毛症もその一つです。
円形脱毛症では、免疫の主役であるリンパ球(T細胞などの白血球)が間違って毛を生み出す工場である「毛包(もうほう)」を攻撃してしまいます。毛包は本来免疫から守られた「特別な空間」ですが、この防御が破綻し、毛包周囲に炎症が起こっている状態です。顕微鏡で脱毛部位を調べると、血管から毛包周囲にリンパ球が集まり、毛根部分を取り囲んでいるのが確認されています。リンパ球に攻撃された毛は栄養や成長シグナルが絶たれ、毛根が萎縮して成長が止まり、抜け落ちてしまいます。

通常、円形脱毛症で抜けてしまった毛も、免疫による攻撃が収まれば時間と共に再生する可能性があります。しかし、なかなか治らず脱毛が長引く場合、毛包周囲では慢性的な炎症が続いていると考えられます。この慢性炎症が毛の再生を妨げる一因として、近年「モヤモヤ血管」の存在が注目されています。
モヤモヤ血管とは、炎症によって新たにできた異常な細い血管のことです。これら不要な血管網が炎症部位に残ってしまうと、壁が脆く穴だらけの未熟な血管であるため、そこから炎症を起こす免疫細胞が周囲組織に漏れ出しやすくなります。これにより、炎症がなかなか収まらず毛包の回復が遅れると考えられています。円形脱毛症の場合、炎症がある限り髪の毛は成長期に戻れず、休止期(抜ける準備状態)が続いてしまいます。
Q:円形脱毛症になりやすい人はどんな特徴がありますか?
![]()
円形脱毛症は誰にでも起こりうる病気ですが、発症しやすい人、あるいは繰り返しやすい人にはいくつかの共通点が知られています。
- 自己免疫疾患を持つ人
バセドウ病や橋本病(甲状腺疾患)、尋常性白斑、SLE(全身性エリテマトーデス)、1型糖尿病など、他の自己免疫疾患を合併している場合、円形脱毛症を起こしやすいとされています。 - 精神的ストレスが強い人
強いストレスや心身の疲労は免疫バランスを乱し、発症や再発の引き金になることがあります。 - アトピー素因のある人(特に小児・若年者)
円形脱毛症患者の20〜40%にアトピー性皮膚炎の既往があると報告されています。アトピー合併例は治療に抵抗しやすく、慢性化しやすい傾向があります。 - 遺伝的要因のある人
家族に円形脱毛症や自己免疫疾患を持つ方がいると、発症リスクが高まります。免疫に関わる遺伝子(HLAなど)が関与している可能性が報告されています。 - 小児期発症(早期発症例)
小児の頃に発症すると、再発や慢性化のリスクが高いとされています。 - 発症年齢が若い人
特に10代〜30代の若い世代で発症が多くみられます。 - 女性
男女差は大きくはありませんが、女性は自己免疫疾患全般が多いため、結果的に円形脱毛症もやや多いとされています。 - 環境因子が関与する場合
ウイルス感染、ワクチン接種、出産、季節の変わり目など、免疫のバランスが大きく変化するときに発症や再発を経験する人もいます。 - 難治化・再発しやすいタイプ
全頭型・汎発型まで広がった例、アトピー合併、小児期発症などは特に再発・慢性化しやすく、長期の治療が必要になることがあります。
このように、円形脱毛症には「なりやすい体質」や「再発しやすい特徴」があることが知られています。ただし、当てはまるからといって必ず起きるわけではありません。大切なのは、「なぜ繰り返してしまうのか」を正しく理解し、適切な治療と生活習慣の工夫を続けることです。
Q:円形脱毛症はどれぐらいで治りますか?
![]()
円形脱毛症の治癒までの期間は、個人差が非常に大きいことが特徴です。脱毛の範囲、発症年齢、合併症(アトピーや甲状腺疾患など)の有無によって大きく左右されます。
- 軽症例:
小さな円形脱毛斑1~2個であれば、自然に発毛が始まり 3~6か月程度で改善することも少なくありません。 - 中等症:
複数箇所に脱毛斑がある場合、半年から1年程度かかることが多く、治療の継続が必要です。 - 重症例:
全頭型や汎発型では 1年以上かかる場合や、治療が困難となることもあります。
さらに、小児発症例やアトピー体質を持つ方は再発・慢性化のリスクが高く、長期の経過観察が必要です。一度改善しても 数年後に再発するケースもあり、「治って終わり」ではなく継続的なセルフケアや通院が再発防止につながります。
重症度や予後の見通しは、皮膚科専門医による評価が不可欠です。毛根の状態を拡大鏡(ダーモスコピー)で確認したり、血液検査で免疫や甲状腺の異常を調べながら、「どのくらいで回復が期待できるか」を判断します。
Q:円形脱毛症でやってはいけないことは何ですか?
![]()
円形脱毛症では、毛を作る毛包を守ることがとても重要です。以下の行為は円形脱毛症を悪化させたり再発させたりする原因になるため、避けるようにしましょう。
- 毛を引っ張ったり抜いたりすること
毛包を傷つけ、髪の再生を妨げます。円形脱毛症が治りにくくなる大きな要因です。 - 強い牽引や摩擦刺激
強いブラッシング、ポニーテール、きつい髪型、ヘアアイロンの過度な使用は、毛根に負担をかけて症状を悪化させます。 - 刺激の強い化学処理
髪を染めたりパーマなどの薬剤は頭皮に強い刺激を与えます。特に治療中や毛が再生し始めた時期は控えることが大切です。 - 生活習慣の乱れ(ストレス・睡眠不足)
強い精神的ストレスや睡眠不足は、免疫の異常を助長し、円形脱毛症の再発リスクを高めます。 - 自己判断での治療中断
髪が生え始めても医師の指示なく薬や通院をやめると、再び脱毛が進行することがあります。
円形脱毛症は「毛を生やす治療」だけでなく「毛を守る生活習慣」も大切です。毛を引っ張らない、頭皮に刺激を与えない、十分な睡眠とストレス対策をすることが、円形脱毛症の改善と再発予防につながります。
Q:円形脱毛症を改善する方法はありますか?
![]()
円形脱毛症を改善するためには、専門医による早期診断と適切な治療が最も重要です。そのうえで、日常生活でできる工夫が回復を助け再発予防にもつながります。
- 専門医の診察と治療
皮膚科専門医に相談し、ステロイド外用・注射、局所免疫療法、JAK阻害薬など、症状に合った治療を選択しましょう。 - 生活習慣の改善
十分な睡眠は、免疫バランスを整えるための基本です。あわせて、バランスのとれた食事も欠かせません。特に、タンパク質・鉄・亜鉛・ビタミンを意識することで、体の回復力や抵抗力を高めることができます。さらに、適度な運動はストレスの軽減や血流の改善に役立ち、心身の健康維持に大きく貢献します。 - ストレス対策
精神的ストレスは円形脱毛症の再発リスクになります。リラクゼーションやカウンセリングを取り入れて心身を整えましょう。 - 頭皮へのケア
- 過度なブラッシングや牽引は避ける
- 優しく洗髪し、しっかり乾燥させる
- 脱毛部は紫外線から守る
- ウィッグを使う場合は通気性のよいものを選ぶ
円形脱毛症は「治療」と「生活習慣の改善」の両輪で回復が期待できます。免疫を整える生活と、頭皮に優しいケアを続けることが、円形脱毛症の改善と再発予防につながります。
Q:円形脱毛症の治療法にはどのようなものがありますか?
![]()
脱毛症の治療の基本方針は「過剰な免疫反応を抑えつつ、毛包の回復・発毛を促す」ことです。軽症か重症か、脱毛範囲はどの程度かによって選択される治療法は異なります。
- ステロイド局所療法(外用・局所注射)
脱毛部にステロイドを塗ったり注射したりして炎症を抑える方法です。小さな範囲では第一選択となります。 - ステロイドパルス療法(全身投与)
急速に進行する重症例(全頭型・汎発型)で行われることがあります。大量のステロイドを短期間で点滴し、強力に炎症を抑え込みます。入院下で行われるのが一般的です。 - 光線療法(紫外線治療)
紫外線をあてることで免疫の働きを落ち着かせ、毛根の回復を促します。 - 血行促進療法
フロジン液®などを使って頭皮の血流を良くし、毛根の環境を整えます。補助的な治療に位置づけられます。 - JAK阻害薬(内服薬)
自己免疫のシグナルを遮断する新しい薬で、難治性の円形脱毛症にも効果が期待されています。バリシチニブ(オルミエント®)、リトレシチニブ(リットフーロ®)などが承認されています。 - 局所免疫療法(かぶれ療法)
特殊な薬品でわざと軽いかぶれを起こし、免疫の働きを変える治療です。副作用が少なく、ガイドラインでも有効性が評価されています。 - STA動注(浅側頭動脈への動注治療)
超音波で確認しながら極細針で炎症をおこしている血管に薬剤を届け、頭皮の異常な血管(モヤモヤ血管)を減らすことで毛根環境を改善。外来で受けられ薬を直接使わず、副作用が気になる方にも適した新しい治療法です。
詳しい症例や治療法ついては、以下の実例もご参照ください。
円形脱毛症の治療にはどんな副作用がありますか?
![]()
治療によっては副作用が出ることがあります。
- ステロイド局所療法:
皮膚がへこんだり、色が白くなることがある。 - ステロイドパルス療法:
むくみ・不眠・胃の不快感などが出る場合があり、血糖値上昇や感染症リスクもある - JAK阻害薬:
感染症にかかりやすくなる、肝機能や血液検査の異常が出る場合がある - 動注治療:
注射部位の内出血などがありますが、軽度であることが知られています。
治療の効果とリスクを理解し、医師と相談しながら進めることが大切です。
Q:円形脱毛症に長年悩んでいます。市販の育毛剤や内服薬を試してきましたが効果が乏しく、副作用も心配です。薬を使わずに治療する方法はありますか?
![]()
従来、脱毛症の治療といえば生活習慣の改善や外用薬(育毛剤)、内服薬(ホルモン関連薬や発毛促進薬)が中心でした。しかし、近年の研究で、慢性化した円形脱毛症(脱毛症)の背景には「モヤモヤ血管」と呼ばれる異常に増殖した血管が関与していることがわかってきました。これらの血管は頭皮に慢性的な炎症や血流のアンバランスを引き起こし、毛根の機能低下や抜け毛につながると考えられています。
この新しい知見に基づき、「STA動注」という方法を脱毛症に応用しています。超音波を用いて27G(ゲージ)という非常に細い針で血管を穿刺し、異常な血管が集まる頭皮の部位まで薬剤を届けることで、モヤモヤ血管を選択的に減らし、毛根の環境を改善します。薬を直接使わずに、頭皮の血流と炎症をコントロールすることができるため、従来の治療で効果が乏しかった方や、副作用が気になる方にも新しい選択肢となっています。
詳しい症例や治療経過については、以下の実例もご参照ください。
<参照>
(日本皮膚科学会 編. 円形脱毛症診療ガイドライン 2024. 日本皮膚科学会雑誌, 134(3): 323–370, 2024.
Gilhar A, Etzioni A, Paus R. Alopecia areata. N Engl J Med. 2012;366(16):1515-1525.
Alkhalifah A, Alsantali A, Wang E, McElwee KJ, Shapiro J. Alopecia areata update: Part I. Clinical picture, histopathology, and pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2010;62(2):177–188.
Crispin MK, Ko JM, Craiglow BG, et al. Safety and efficacy of the JAK inhibitor baricitinib for the treatment of alopecia areata: Phase 2 results. N Engl J Med. 2022;386:1687–1699.
King B, Ohyama M, Kwon O, et al. Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia Areata. N Engl J Med. 2022;386:1687–1699.
Gupta AK, Carviel J, Abramovits W. JAK inhibitors for alopecia areata: a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(2):215–225.
Messenger AG, McKillop J, Farrant P, McDonagh AJG, Sladden M. British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of alopecia areata 2012. Br J Dermatol. 2012;166(5):916–926.
島田 謙. 円形脱毛症に対する局所免疫療法. 皮膚病診療 2019;41(5):563–568.
Shibuya M, Okuno Y, et al. Abnormal neovascularization (“moyamoya vessels”) and chronic inflammation in musculoskeletal pain: potential targets for embolization therapy. Pain Physician. 2021;24:E123–E134.
奥野祐次, 澁谷真彦. 運動器カテーテル治療(TAME)による異常血管へのアプローチと慢性炎症制御. 日本IVR学会雑誌. 2022;37(1):45–52.
著者プロフィール
奥野祐次 M.D., Ph.D.(医師・医学博士)
オクノクリニック 総院長
専門分野:慢性疼痛、モヤモヤ血管に対する血管内治療、カテーテル治療・動注治療、画像診断(MRI・エコーを活用した精密な痛みの診断)
2006年3月、慶應義塾大学 医学部 卒業。2008年より放射線科医として血管内治療に従事し、2012年3月、同大学大学院医学研究科博士課程を修了(研究テーマ:「病的血管新生」)。同年4月より江戸川病院にて運動器疾患に対する血管内治療を専門に担当。2014年には同院「運動器カテーテルセンター」センター長に就任。2017年10月、神奈川県・センター南にて「オクノクリニック」を開院。
現在東京を中心に全国10院を運営するオクノクリニックの総院長。運動器カテーテル治療の専門医として、長年にわたり痛みに悩む患者の治療に取り組んでいる。

慢性痛についてのお問い合わせ・診療予約
![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel2.jpg)
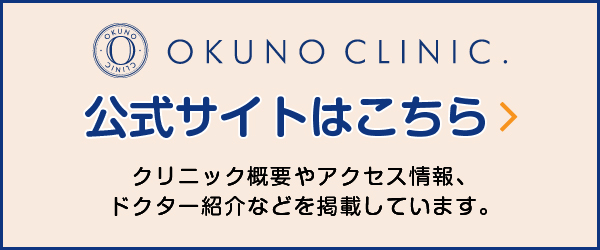
![オクノクリニック [新規予約受付時間]10:00-16:00[休診日]日曜日](images/tel1.jpg)